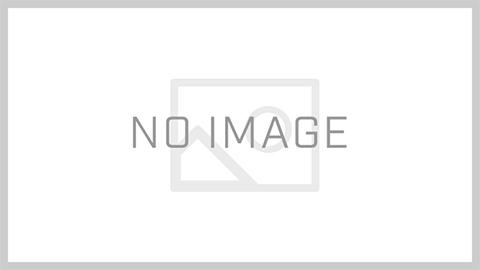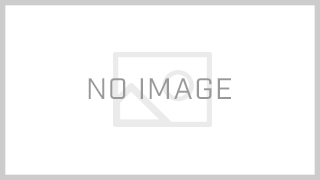七夕の夕食にそうめんを食べ始める風習って、いつからなんだろう?
といった、疑問にお答えしますね。
この記事で書いてあること
- 七夕の食べ物の由来は
- 七夕の食べ物、夕食にはそうめん!その風習の由来は?
- 七夕の食べ物、そうめん以外の夕食紹介!
七夕の食べ物の由来や、夕食にそうめんを食べる風習の由来、そうめん以外の七夕の夕食献立の紹介などのご紹介したいと思います。
七夕の食べ物の由来は?

七夕の食べ物は、正式には七夕の「行事食」と呼ばれます。
七夕の行事食の由来がどこにあるのかといったことを、こちらでご紹介したいと思います。
七夕は、桃の節句や端午の節句などと同じ、5節句の一つに挙げられます。
それぞれの御節句には、「行事食」というものがあり、桃の節句では、「ひなあられ」が、端午の節句では、「柏餅」や「ちまき」を指します。
この辺りは、皆さん慣れ親しんでおられると思います。
意外と知られてないのですが、七夕の節句の行事食というのは、「そうめん」になります
七夕の食べ物の由来、索餅って何?
本日七夕でしたね!平安時代には七夕に索餅を食べて病除けを祈願していたそうです。索餅は当店でも扱っている唐菓子のことです。
テイクアウトもしていますのでぜひー!#ことのまあかり #唐菓子 https://t.co/XuaqvI90Rn pic.twitter.com/l7zcjwNpPO— 奈良の雑貨とカフェBAR ことのまあかり (@kotonomaakari) July 7, 2017
この、七夕の節句で「そうめん」を食べる由来ですが、 他の五節句と同じ中国から伝わったものになります。
中国の伝説で、7月7日に幼くして亡くなった、皇帝の子供の祟りで疫病が流行し、その祟りを抑えるために、その子供の好物だった「索餅(さくべい)」というお菓子をお供えしたのが始まりと言われています。
その索餅(さくべい)というお菓子が、その伝説から中国の七夕の食べ物になっていたのですが、それが日本に伝わった頃に、そうめんに変わったのではないかと言われています。
索餅(さくべい)は、水と小麦粉を細く練って、ツイストした、揚げドーナツのような見た目です。
それが日本では、同じように小麦粉を細く練ったものとして、そうめんに代用されるようになったと言われています。
「索餅」は、「索」に「餅」と書きますが、これが日本に伝わってきて「索麺」となり、 「索」が「素」に変化して、そうめんになったと言われています。
七夕の食べ物、夕食にはそうめん!その風習の由来は?
今日も一日お疲れ様でした🍀
最高29度まで上がり、
蒸し暑〜い石川でした🥵夕方やっと涼しくなって来た😸👌
一日早いけど七夕メニュー⭐️
本日の夕食💕
七夕そうめん🎋
鶏肉の竜田揚げ
とうもろこし🌽←地元産で甘〜い🎶😸
ぶどう🍇 pic.twitter.com/F6netPC5xB— ダッフィーさん (@ijGHwt1sJYTxCkM) July 6, 2019
七夕の節句の行事食は、中国では今でも索餅で、日本では元来「そうめん」、ということなのですが、意外と日本でも「七夕の夕食にそうめん」というものが、実はピンとこない地域の方が多いのです。
七夕の食べ物、夕食にそうめんの風習はいつから
中国から、奈良時代に、そうめんの原型である索餅(さくべい)が、それこそ西日本側の日本へ、中国の風習とともに伝えられ、すでに平安時代には、七夕にそうめん(当時は索餅)をお供えすることということが、儀式の中で定められたりしています。
「索餅」がどうやって、「そうめん」を夕食に食べる風習に変わっていったかというのは、定かではないのですが、七夕の文化が庶民に広がるにつれ、より食べやすい「そうめん」になったという説や、 織姫と彦星の伝説に基づいた、天の川を模したそうめんを夕食に食べるようになったなど様々な説があります。
色付きそうめんの由来は
さらに興味深いのが、色付きそうめんの由来です。
麺の一部にピンクや黄色、緑といった色付きのそうめんを、見かけたことがあるかと思いますが、あれは江戸時代に、中国から伝わった、五行思想に繋げて、七夕の五色の短冊と同様に、魔除けや厄除けを意味して、食べるという文化が広がっていったそうです。
七夕の食べ物:仙台や東北、北海道では夕食にそうめんが常識
七夕の伝統的な食べ物が、そうめんであることは間違いありませんが、意外と風習として定着していない地域も多いです。
この七夕の食べ物「そうめん」文化は、仙台や東北、北海道に残っているものの、特に西日本では、その文化はあまりなくなってきたと言うのが、他の五節句とは違うところです。
中国から西日本へ伝わってきた、七夕の「そうめん」文化が仙台や東北、北海道にしか残っていないと言うのもとても興味深いですね。
七夕の食べ物、そうめん以外の夕食紹介!
本来七夕に食べる夕食といえば「そうめん」なのですが、肝心の七夕そうめん文化は、仙台をはじめ東北地方や北海道を除いて残っていないとご紹介しました。
それではその他の地域では、七夕でそうめん以外にどんな食べ物を、食べているのでしょうか?
七夕の食べ物としてそうめん以外に定着している夕食の献立をご紹介します。
七夕の食べ物:ちらし寿司
こんばんは(^-^) 7/7 夕食🎋
七夕ちらし、七夕素麺、ホヤとキュウリの酢の物、ところてん、オレンジ🍊ムースも手造りです🍴 pic.twitter.com/VnPwmwAr0B— ♡晴海♡ (@harusunifu) July 7, 2014
七夕の食べ物として、関西を中心に人気があるものがちらし寿司です。
ちらし寿司は、もともと錦糸卵や人参、でんぶなどといった、色とりどりな食品が使えることで、華やかに七夕の食卓を彩ることができます。
普段は子供が食べないような、オクラや人参なども、星に見立てて食べさせるという、お母さんのアイデアも光ります。
最近ではひな祭りも、ちらし寿司という文化が定着しつつある関西ですが、七夕にも星形に切った人参やオクラで飾り付けしたり、そうめんを天の川に見立ててトッピングしたり、ちらし寿司を合わせて、華やかな見た目の料理が出来上がります。
七夕の食べ物 カレーライス
今日も一日お疲れ様でした🍀
🎶笹の葉さ〜らさら〜🎋
七夕の夜は、曇り予報☁️
星空は見えるかなぁ⭐️🤔
妹が
ミスド買って来てくれた〜😋🙌
しかし、食べすぎ⁉️🤣💦本日の夕食💕
七夕カレー
豚肉のネギ塩
ぶどう🍇
デザートはドーナツ🍩🍩←二個😳 pic.twitter.com/pWRO8GihKQ— ダッフィーさん (@ijGHwt1sJYTxCkM) July 7, 2019
ほかに七夕の食べ物で人気があると言えば、カレーライスではないでしょうか?
こちらも人参やチーズなどで星型にトッピングを作って、カレーを天の川に見立てます。
もうそれだけで、七夕の雰囲気が出てきて、子供もモリモリ食べてくれます。
最近では そうめんの行事食の文化をあやかって、ご飯の代わりに、そうめんにカレーをかけるという方もいらっしゃるようです。
七夕 食べ物の由来は?、夕食にそうめんを食べる風習の由来を紹介!
七夕の食べ物の由来と、夕食にそうめんを食べる風習の由来:まとめ
七夕スイーツ✨
天の川羊羹を作りました🎋友達に教えてもらったコツで、寒天と羊羹部分が完全にくっ付いて嬉しい😆(桜羊羹の時は、じつは層が分離してたのです…)
雨ばかりですが、今年は星が見えますかねー? pic.twitter.com/43ehaeiXA3
— ソイ🌱ハリネズミ (@Soy_Hedgehog) July 5, 2019
七夕の食べ物「そうめん」の由来、夕食にそうめんを食べる風習の由来などをご紹介をしてきましたがいかがでしたでしょうか?
日本の行事、五節句のうちの一つである、七夕の食べ物の由来や、そうめんを食べる風習の由来、そして今流行りの七夕の夕食なども、ご覧いただけたかと思います。
七夕の食べ物が、「そうめん」なんて知らなかったと言う方にも、一度ぜひ、そうめんを絡めた、七夕の夕食アイデアにチャレンジしてもらえたらと思います。